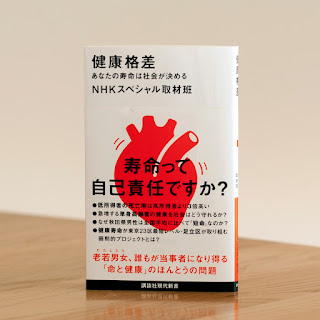こんにちは。ひとりです。
私は映画が好きで、毎週1本は観たいと思っています。ブログで紹介したものといえば下記の投稿が挙げられます。
2018/1/5
映画 キングスマン。マシュー・ボーン監督の過激アクション

2017/12/3
“それ”が見えたら… 。ホラー版 スタンド・バイ・ミー
2017/11/27
京大塗れの週末。こうして出逢ったのも、何かのご縁

2017/11/24
映画 ギフテッド。温かみのある音楽が物語に彩りを

映画のチケットはネットで購入か、映画館で購入か
映画観賞についての調査結果をネット広告会社が16日、発表しました。それによると、インターネットで映画チケットを購入する人は57.3%と、映画館で購入する42.7%を上回ったそうです。(2017年10~11月、男女3,939人を対象にアンケート)
映画チケットを購入する比率は、2016年の調査よりも10.1ポイント上昇しています。鑑賞当日より前にネット予約するとの回答は41.9%で、ネット予約者の3人に2人は前日までにチケットを手に入れています。
また映画情報をネットから収集する比率は4割を超え、劇場予告(21.8%)やテレビ(15.7%)などからの情報を上回っています。
映画予告。魅力あふれる90秒
上映前のスクリーンには公開予定の映画予告が流れています。時間にして30秒から90秒程度のもので、映画の公式サイトには必ず掲載されています。私はこの予告が好きです。
予告編も映画を観る人の趣向に応じて変わってきているといいます。例えば劇場側の要請で、30秒、60秒といった短めの予告編を求められることが増えているそうです。制作者と劇場側の要請。その間にいいとこ取りで、原形をとどめなくなってしまうこともしばしば。ストーリーの説明が多く、内容の分かりやすい予告編が好まれるようになったともいわれます。
予告編では映画本編では記憶に残らないような何げない場面が印象的に用いられていることも多く、私は映画本編を観た後で、もう1度予告を観ることもよくあります。
フィルムの1コマは、時間にすると24分の1秒。流れてしまえばほんの一瞬ですが、その1コマがあるかないかで胸が高鳴ったり、違和感を覚えたりします。不思議ですね。