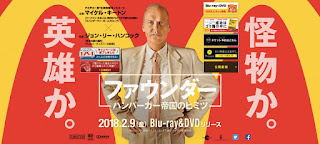こんにちは。ひとりです。
映画「ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ」を観ました。ファウンダー(founder)とは創業者の意味で、映画の原題「THE FOUNDER」にも使われています。
邦題にもあるようにハンバーガー帝国が築き上げられるまでの物語です。このハンバー帝国は全世界で今や約3万6000店舗を構え、世界中の約1%が毎日食べているという、言わずと知れたマクドナルド(McDonald’s)です。
ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ
主人公のレイ・クロックは、ファストフード店「マクドナルド」のフランチャイズ化を進めて、世界的チェーンに育て上げました。ミルクセーキ機の販売員として全米を回るうちに、効率的なハンバーガー調理システムを導入したマクドナルドに出会い、フランチャイズ権を獲得。52歳でマクドナルドシステムを創業した経緯が描かれています。
本作の構想はマーク・ノップラーの「ブーム・ライク・ザット」の歌詞に描かれた、マクドナルドの誕生秘話への着目から始まったといいます。
Mark Knopfler - Boom, Like That (Promo Video) OFFICIAL
映画の前半ではレイ・クロックを応援したくなりますが、後半では彼のやり方に反感を覚えるようになります。全ての部分で良い人、悪い人とは割り切れないのが現実ですが、映画にはどうしてもそれを求めがちになってしまいます。そのバランスの取り方は観る側にヒリヒリとした駆け引きの緊張感として伝わってきます。
主人公の生き方もそうですが、革新的なファストフードシステムが誕生するまでのシーンは興味深いです。またマクドナルドのロゴマークや店舗の外観、厨房スタッフの帽子は、当時を忠実に再現したものでそちらにも注目が集まっています。
監督はジョン・リー・ハンコックで、「ウォルト・ディズニーの約束」(2013年)でも今作同様に、映画「メリー・ポピンズ」の製作裏で起きていた原作者パメラ・トラバースとウォルト・ディズニーの対立を描いて、ディズニーの暗部を露わにしています。
フランチャイザー成功のエッセンスが凝縮
新作映画の場合、評論家のプレビューが上映前に新聞や雑誌に掲載されます。今作の場合もそれはほかと同じですが、掲載された媒体に特徴があります。情報誌や男性、女性ファッション誌の映画コラム欄のほかに、飲食業界や宿泊業界を始めとする経営誌、経済誌にも多数紹介されている点です。
また堀江貴文さんがラジオ番組「日曜シネマテーク」に出演した際には、2017年のベスト3映画の1つに挙げられています。
以下引用
この映画は経営者が絶対に観るべき映画です。マクドナルドのファウンダー(創業者)だったレイ・クロックという人物を描いています。もともとマクドナルドはカリフォルニア州のマクドナルド兄弟が1940年代に作ったハンバーガー屋でした。
当時のアメリカはモータリゼーションが進む中、ドライブスルーが大人気だったのですが、派手な格好の女の子がローラースケートをはいてハンバーガーを持ってくるようなスタイルは、いろいろトラブルも起きていました。そこで工場のようなライン化を取り入れ、大成功を収めたのがマクドナルドです。
レイ・クロックは訪問販売の営業マンをしていたのですが、マクドナルドに出会って衝撃を受けます。そしてマクドナルドを大規模なフランチャイズ展開に導こうと試行錯誤する……というのがこの作品。どうやって世界最大のフランチャイザーが生まれたのか、そのエッセンスがこの映画に詰まっています。
ちなみにほかの2本は、「君の名は。」と「ハドソン川の奇跡」です。
主人公レイ・クロックとドナルド・トランプ米大統領
行動力と粘り強さで夢をつかむ主人公レイ・クロックは、一方で人のふんどしで相撲を取る、ずる賢い人物でもあります。前向きで努力家でありながら、成功のためには手段を選ばない、善人とも悪人とも言えない人物を、マイケル・キートンが絶妙に演じています。
劇中、セールスがうまくいかないレイが、レコードで演説を聞く場面があります。この演説の主はノーマン・ビンセント・ピールで自己啓発の元祖といわれています。「ポジティブ・シンキング」という言葉の生みの親でもあります。そしてドナルド・トランプ米大統領にも影響した人物です。
後半に見せるレイの強引な手法は、ドナルド・トランプ米大統領を彷彿とさせます。この映画がアメリカで公開されたのは偶然にも2017年1月20日。大統領就任式の日でした。
ブランディングの重要性を理解しているという点で、レイ・クロックとドナルド・トランプ米大統領に共通点があります。特に名前のブランド力でレイは、自分の名前「Kroc(チェコ系)」では商機なしとみて「マクドナルド(スコットランド・アイルランド系)」に固執しています。なにせマクドナルドという名前に惚れ込み、商標権を買い取ったのですから。
一方ドナルド・トランプ米大統領は、ビジネスで成功した自身の商号が持つ影響力を理解して、大統領に就任する前にも後にも生かしています。
現在も残る1号店は、マクドナルドミュージアムに
レイ・クロックは1954年、マクドナルドを開いたマクドナルド兄弟と52歳で出会い、同兄弟との確執を経て1961年にその権利を買収しています。その後、今日のマクドナルドの前身となるマクドナルドシステムを創業し、以降はチェーン展開によって世界にマクドナルドを築き上げました。
マクドナルド兄弟がつくった1号店は劇中にも描かれていますが、ロサンゼルス郊外のサンバーナーディーノに残っています。
レイ・クロックはマクドナルドの経営権を得た後も、この店だけは兄弟に残しました。しかしマクドナルドというブランドの商号はレイが所有していたため使えずに、兄弟は別の名称でハンバーガーショップを運営することに。しかし、うまくいきませんでした。
「マクドナルドミュージアム」として現在は運営され、マクドナルドグッズとともに入口にはファウンダー(創業者)であるマクドナルド兄弟を顕彰するプレートが設置されています。兄弟から店を買い取り、ミュージアムとしたのは日系三世のアルバート・オクラという人物です。
広い敷地に建つゴールデンアーチからは、1950年代に進んだモータリゼーションの影響もあり、手早く済ませられる食事、ファストフードがいかに時流に乗っていたかを感じ取れます。
ちなみにケンタッキー・フライド・チキン(KFC)もマクドナルドと双璧をなすファストフードチェーンです。
カーネル・サンダースの手記がウェブサイトで公開
ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)の創業者として知られるのがカーネル・サンダースです。カーネルがフランチャイズチェーン展開を開始したのが1952年です。62歳でフライドチキンをワゴン車に積んで全米各地を回り始め、約5年後には全米とカナダで400店舗の一大チェーンを築き上げたといいます。
KFCホールディングスのウェブサイトには、カーネル・サンダースの手記が公開されています。504ページにも渡るPDFデータがダウンロードできます。
カーネル手記 |日本KFCホールディングス株式会社 KFC Holdings Japan, Ltd.
「ヒト・モノ・カネ」で映画を観ると
経営誌や経済誌にも取り上げられている通り、この映画は経営的視点でも楽しめます。例えば「ヒト・モノ・カネ」で取り上げると。
1)ヒト
52歳で出会ったのがハンバーガーショップを営むマクドナルド兄弟です。セールス電話のやりとりから興味を持ち、実際に店を訪れることで成功への道が生まれました。また自身が立ち上げた店では、肉の焼き方が上手な青年を見つけると、後に自身の右腕として引き立てています。資金繰りに苦しんでいた時に銀行の外で声をかけられたコンサルタントを会社に迎え入れます。見込んだヒトを、自分にはない能力を持つ人を口説いて成長してきた過程が見えます。
2)モノ
ハンバーガーショップのお客を待たせない「スピード・サービス・システム」に目を付けます。また街中を見上げると目に入る、教会の十字架や国旗と同様に店のアイコンとなる「ゴールデンアーチ」。さらにその商号などモノそのものではなくサービスやブランドに着目して買収を仕掛けています。
3)カネ
マクドナルドの全米展開のために自宅を担保に資金を得ています。また店舗数拡大のためにも大胆な手を打ちます。ビジネスにおいてお金を借りて投資をすることは成長への一歩であり、そこに必要なのが時期と決断です。
成功について、レイ・クロックが自伝に書き記しています。
If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from that person’s angle as well as from your own.
成功の秘訣というものがあるとしたら、それは他人の立場を理解し、自分の立場と同時に他人の立場からも物事を見ることのできる能力である。
『成功はゴミ箱の中に レイ・クロック自伝 — 世界一、億万長者を生んだ男 マクドナルド創業者』レイ・クロック著(邦訳:プレジデント社)より。
善悪割り切れない「成功者」の姿を映画で見た後では皮肉の1つも言いたくなりますが、成功すれば正義と捉えられがちな世間では成功者の言葉の1つとして残っているのでしょう。何事も後々に意味が生まれる世の中です。